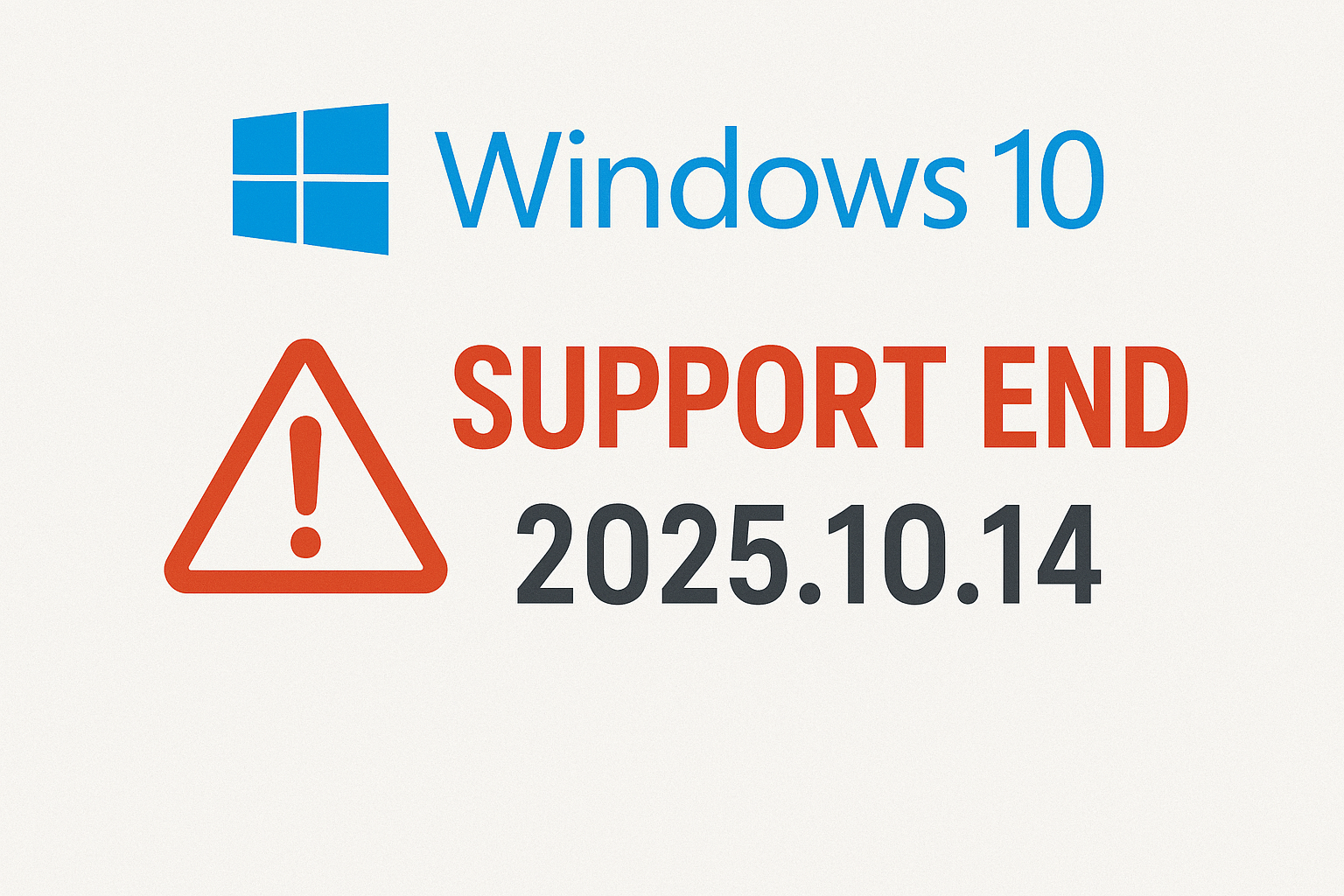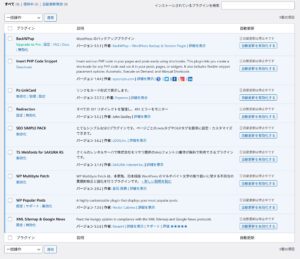2025年10月14日、世界中で数億人が利用してきた Windows 10 がついにサポート終了を迎えました。 2015年の登場以来、家庭用PCから企業の基幹システム、教育現場まで幅広く浸透し、インターネット社会の基盤を支えてきたOSが、ついにその役割を終えます。
「まだ動くから大丈夫」と思う人も少なくないでしょう。ですが、サポート終了は単なる“区切り”ではなく、利用者にとっては「安全にPCを使い続けるための行動を迫られる転換点」です。この記事では、Windows 10の歩みを振り返りつつ、終了の意味と今後の選択肢を整理します。
背景
Windows 10は、マイクロソフトが「最後のWindows」と位置づけ、従来の「新バージョン発売」型から「継続的アップデート」型へと大きく舵を切った最初のOSです。
- 2015年7月:リリース開始。当初はWindows 7/8.1からの無償アップグレードを提供し、短期間で普及を拡大。
- 2017年以降:半年ごとの大型アップデートで新機能を追加。CortanaやEdgeブラウザなど新しい試みも導入。
- 2021年:後継のWindows 11が登場。デザイン刷新とセキュリティ強化を前面に打ち出す。
- 2022年以降:アップデートは年1回に縮小。22H2が最終バージョンとなり、事実上「延命フェーズ」に。
10年間で、クラウド利用の拡大、リモートワークの普及、セキュリティ脅威の高度化といった社会変化を支えたのがWindows 10でした。だからこそ、その終了は「時代の節目」として重みを持ちます。
終了の意味
サポート終了とは、単に「更新が止まる」ことではありません。最大の意味は セキュリティ更新が提供されなくなる ことにあります。
OSは常に新しい脆弱性が発見されます。通常であれば、マイクロソフトが修正プログラムを配布し、利用者はWindows Updateを通じて自動的に防御を強化できますが、終了後は、その仕組みが完全に止まります。
つまり、見た目は正常に動いていても、時間が経つほど“穴だらけの城壁”を使い続ける状態になります。これは個人利用にとどまらず、企業や教育機関にとっては重大なリスクを意味します。
利用者への影響
個人ユーザー
- 新しいウイルスやマルウェアに対して無防備になる。
- ネットバンキングやオンラインショッピングでの利用は特に危険。
- 新しいアプリや周辺機器が非対応となり、利便性も低下する。
法人ユーザー
- 情報漏洩やシステム侵入のリスクが増大。
- 業界によっては「サポート切れOSの利用」がコンプライアンス違反となる。
- サイバー攻撃の標的になりやすく、経営リスクに直結する。
教育機関
- 古いPCを使い続けると、生徒の学習環境や個人情報が危険にさらされる。
- ICT教育の現場で「安全な環境を提供できない」という課題が浮き彫りになる。
「まだ使えるから残す」という発想は、セキュリティの観点からは通用しません。むしろ「動くうちに移行する」ことが最も合理的な選択になります。
移行の選択肢
- Windows 11 へアップグレード
- PCが要件を満たしていれば無料で移行可能。
- TPM 2.0やセキュアブートなど、セキュリティ機能が強化されている。
- UI刷新により、より直感的な操作が可能。
- 新しいPCへの買い替え
- 要件を満たさないPCは買い替えが現実的。
- 最新CPUやSSDを搭載したPCは、性能面でも大幅に向上。
- 長期的に見れば、買い替えの方がコスト効率が良い場合も多い。
- 拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)
Windows 10のサポート終了後も、どうしてもすぐに移行できない環境のために「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」が用意されています。
- 無料ESU:2025年10月14日から 2026年10月13日までの1年間限定 で提供。MicrosoftアカウントとWindows Backupの利用など条件を満たせば、個人ユーザーでも無償でセキュリティ更新を受けられる。
- 有料ESU:2026年10月以降も契約更新により最大2028年まで延長可能。主に法人や教育機関向けで、レガシーシステムを抱える場合の“延命策”として利用される。
まとめ
Windows 10のサポート終了は、単なるOSの終焉ではなく、「安全にPCを使い続けるための行動を促す合図」。
10年間の歴史を振り返れば、Windows 10は確かに時代を支えました。しかし、これからの時代を支えるのはWindows 11やその先の新しい環境です。
利用者に求められるのは「まだ動くから残す」ではなく、「未来に備えて移行する」という発想。 その選択が、これからの10年を安心して過ごすための第一歩となります。